「ブログを再開したいけど、何を書けばいいのか分からない」
そんな悩みを持つ人は、思っている以上に多いです。
実を言うと、自分もまったく同じ状況でした。
何度もブログに挑戦しては挫折し、そのたびにテーマを変えて、結局どれも中途半端に終わっていました。
頭の中では「稼げるテーマを選ばなきゃ」と焦りつつ、心の中では「本当にこれを書き続けられるのか?」という迷いがつきまとう。
その結果、どの記事も自分らしさがなく、誰に何を伝えたいのかが分からないまま終わっていたんです。
けれど、ある時出会ったメンターから「方向性は最初から完璧じゃなくていい」と教わってから、考え方が大きく変わりました。
この記事では、かつてノウハウコレクターだった自分が、ブログの方向性を定めるために実際に意識した3つの視点を紹介します。
この3つの軸を持つようになってから、ブログを書くのが驚くほど楽になりました。
「続けられない」と悩んでいる人はこちらの記事も参考になります👇
ブログを続ける力をつけるマインドセットとは?習慣化にして挫折しないコツを紹介
ブログの方向性を決める視点①自分が語れるテーマを軸にする

ブログのテーマを選ぶとき、多くの人が「好きなことを書こう」と言います。
たしかにそれも大切ですが、長く続けるには“好き”よりも“語れる”テーマのほうが安定します。
語れるテーマというのは、知識だけでなく、自分の経験が伴っている分野のことです。
たとえば、初心者時代の失敗談や、実際に試してみた比較・検証など。
こういった実体験には、検索上位の記事にはないリアルな説得力があります。
自分が最初にやってしまったのは、流行っているテーマを真似して始めることでした。
「副業」「投資」「AIライティング」…そのとき話題のキーワードを追いかけて、結果的にどれも中途半端になってしまったんです。
いくら稼げそうでも、自分の体験や想いがないと、すぐに書くことがなくなってしまいます。
あるとき、メンターから「過去の自分に教えてあげたいことを書け」と言われてハッとしました。
たとえば、独学でブログを始めて稼げなかった時期の失敗や、どうやって再挑戦する気持ちを取り戻したのか。
そういう“語れるテーマ”は、自分だからこそ書ける唯一のコンテンツなんですよね。
その瞬間、ブログの方向性がふっと軽くなりました。
「自分の経験を書いていいんだ」と思えたことで、自然に言葉が出てくるようになったんです。
書きやすさの正体は「共感」
語れるテーマの強みは、書きやすさだけではありません。
読んでくれる人が「自分と同じだ」と共感してくれる可能性が高いんです。
自分が書いた記事に「まさに今同じことで悩んでました」とコメントが届いたとき、初めて“誰かの役に立てた”という実感が湧きました。
情報量よりも、“リアルな声”が読者に届く。
これが、語れるテーマを選ぶ最大のメリットだと今は感じています。
テーマは一度で決めなくていい
最初から完璧に決めようとすると、逆に動けなくなります。
方向性は“行動しながら見えてくるもの”です。
10〜20記事ほど書いてみると、自分が自然と熱を込めて語れるテーマが見つかっていきます。
「どんなテーマが正解か」よりも、「どんな話なら続けられるか」を基準に考えると、ブログが一気に楽になります。
ブログの方向性を決める視点②誰に届けたいかを明確にする



次に意識すべきは「誰に向けて書くのか」という視点です。
これが定まっていないと、記事の方向性がブレやすくなります。
昔の自分は、とにかく“たくさんの人に読まれたい”という気持ちで書いていました。
でも、結果的に誰の心にも届かない内容になってしまったんです。
なぜかというと、読者の顔が見えていなかったから。
メンターから言われたのは、「たった一人の理想読者を思い浮かべて書け」ということでした。
その瞬間、「ああ、これは“届ける”ための文章なんだ」と気づきました。
たとえば、今この記事を読んでいるのが「ブログに再挑戦したいけど方向性が分からない男性」だとしたら、書き方も自然と変わります。
「こうすれば稼げます」と突き放すより、「自分も同じだった」と共に悩むトーンの方が響きます。
書いている途中で迷ったときも、「あの頃の自分ならどんな言葉を聞きたいか」を思い出すと、方向性が戻ってくるんです。
理想読者を一人に絞る理由
ターゲットを狭めると、読まれる機会が減るんじゃないかと不安になるかもしれません。
でも実際はその逆で、「この人のために書いた」と思える文章は、不思議と多くの人に刺さります。
具体的な悩みを深掘りするほど、内容が濃くなって、検索エンジンでも上位に上がりやすくなるんです。
SEOの観点から見ても、「再挑戦」「挫折」「ブログ初心者」といった明確な読者像がある記事は、検索意図とマッチしやすい傾向があります。
つまり、“誰に向けて書くか”を決めることが、SEO対策にもつながるということです。
過去の自分が最強の読者像
もし理想の読者像が思い浮かばないなら、過去の自分を読者にすればいいと思います。
自分は独学で稼げなかった頃、何が分からず、どんな情報を欲しかったかを思い出す。
そのときの不安や迷いを言葉にしてあげると、同じように悩む人の心にスッと届きます。
自分の場合、「何から手をつければいいか分からない」「テーマを決めても続かない」という悩みが一番深かったので、そこに焦点を当てて記事を書くようにしました。
結果として、自然と“再挑戦者向けブログ”という方向性が定まっていったんです。
ブログの方向性を決める視点③どんな価値を届けたいかを意識する



最後の視点は「価値」です。
ブログを通じて、読者にどんな変化を届けたいかを意識することで、記事全体の軸が生まれます。
最初の頃の自分は、「どうすればアクセスが増えるか」ばかり考えていました。
しかし、PVを追いかけても、心から満足できる記事にはならなかったんです。
それよりも、「この記事で誰かの不安が少しでも軽くなれば」と思って書いた方が、自然とリピートされるようになりました。
メンターから言われた言葉で印象に残っているのが、「読者に変化を届けるのがブログの本質」という一言です。
たとえば、副業で収入を増やしたい人に実践的な方法を伝えるとか、自分の考えを発信することで自信を取り戻してもらうとか。
そういう“変化”を意識することで、記事の書き方も大きく変わりました。
記事は“情報”ではなく“体験の共有”
ブログを書いていると、「役立つ情報を出さなきゃ」と思いがちですが、本当に読まれるのは“情報”より“体験”です。
自分の体験を通して得た気づきや感情こそが、読者にとっての価値になるんです。
自分も昔、「SEOに強い構成を完璧にすれば読まれる」と信じていました。
でも、どんなにきれいに構成しても、心のこもっていない記事は読まれません。
逆に、未熟でも本音で書いた体験談の記事のほうが、反応が良かったんです。
だからこそ、「自分だから語れること」を掘り下げて、「それを誰に届けたいのか」を明確にし、「その人にどんな変化を与えたいのか」を考える。
この3つを意識するだけで、ブログの方向性は自然に見えてきます。
続けるうちに“価値”も進化する
最初に決めた方向性が、ずっと同じである必要はありません。
ブログを書き続けていく中で、自分が成長すれば、届けられる価値も変わっていきます。
最初は「挫折しない方法」を発信していた人が、いつの間にか「収益化の具体的ノウハウ」を語れるようになる。
その変化こそが、ブログを続ける醍醐味だと思います。
実際、自分も再挑戦当初は「ブログの習慣化」をテーマにしていましたが、今では「再挑戦して収益を出すまでのプロセス」を発信しています。
テーマは変わっても、根底にある「挫折した人を応援したい」という軸はずっと変わっていません。
まとめ
| ステップ | やること | ゴール |
|---|---|---|
| ① | 自分が語れるテーマを洗い出す | 書ける分野を把握する |
| ② | 理想読者を一人に絞る | 言葉のトーンと方向性を整える |
| ③ | 届けたい価値を明文化する | 記事の軸を作る |
最後に、今回紹介した3つの視点を整理しておきます。
まず、自分が語れるテーマを軸にすること。
次に、誰に届けたいかを明確にすること。
そして、どんな価値を届けたいかを意識すること。
この3つを考えるだけで、記事のブレがなくなり、自然と方向性が定まります。
大切なのは、方向性を“最初から完璧に決めようとしないこと”です。
実際に10〜20記事ほど書いてみないと、自分の本当の得意分野や読者の反応は見えてきません。
最初のうちは「仮の方向性」でいいので、書きながら少しずつ微調整していきましょう。
ブログは、始めるよりも続ける方が難しい。
でも、方向性の軸があるだけで、迷いが減り、書くことが習慣になっていきます。
挫折を何度も経験してきた自分だからこそ言えるのは、「止まって考えすぎるより、動きながら整える方が結果的に早い」ということです。
もし今、ブログのテーマや方向性に迷っているなら、一度立ち止まって「自分が何を伝えたいのか」「どんな人に届けたいのか」をノートに書き出してみてください。
その中に、あなただけの“語れるテーマ”がきっと隠れています。
そして、たった一人の理想読者を思い浮かべながら、等身大の言葉で書いてみてください。
完璧を目指すよりも、まずは伝えること。
それが、再挑戦を続けるための一番の近道だと思います。
🧩 関連記事リンク
👉 [WordPressテーマの選び方|再挑戦ブロガーが注目すべき7つの機能]
👉 [WordPressプラグインおすすめ5選!挫折しないブログにする方法]
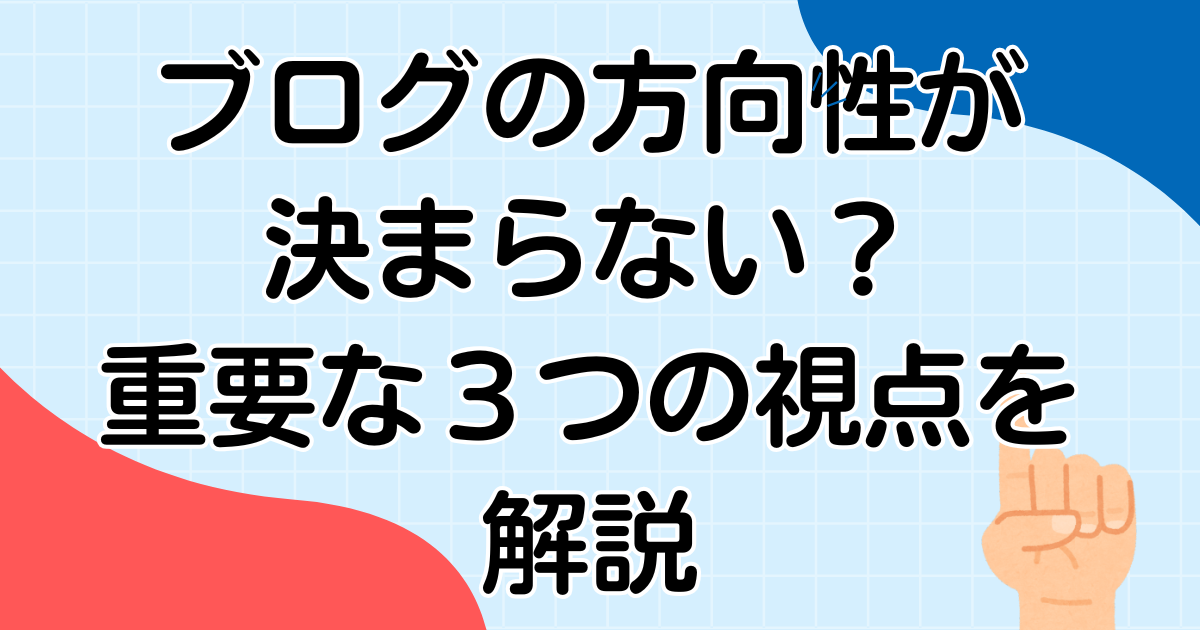
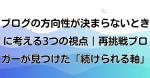

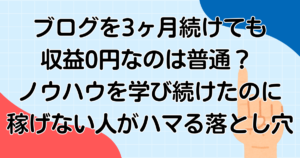
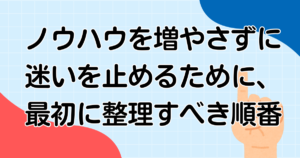
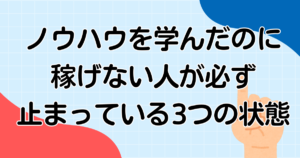
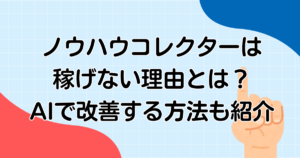
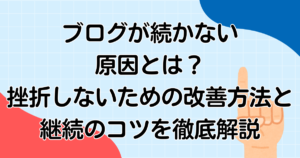
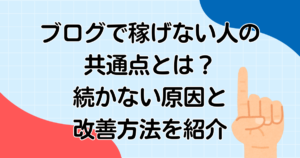
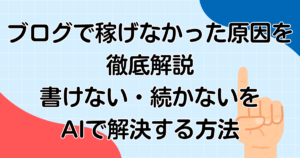
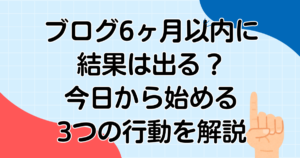
コメント